○君津郡市広域市町村圏事務組合公用文に関する規程
昭和52年12月26日訓令第3号
君津郡市広域市町村圏事務組合公用文に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、本組合における公用文の文体、用字、用語、形式等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公用文の種類)
第2条 公用文の種類は、君津郡市広域市町村圏事務組合文書規程(昭和51年君津郡市広域市町村圏事務組合訓令第6号)第4条に規定するところによる。
(文体)
第3条 文体は、原則として「である」体と「ます」体を基調とし、口語化して平明なものとする。
2 文書は、なるべく区切って短くし、簡潔かつ論理的な表現とし、内容が複雑なものについては、箇条書の方法を用いるものとする。
(文字)
第4条 文字は、原則として漢字と平仮名を用いる。ただし、外国の地名、人名、外国語等を用いる場合、その他特に必要とする場合には片仮名を用いるものとする。
2 漢字及び仮名遣いは、原則として次に定められたものを用いる。ただし、特殊用語、専門用語等については、この限りでない。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(数字)
第5条 数字は、原則としてアラビア数字を用いる。ただし、固有名詞、概数を示す語、数量的な感じの薄い語、慣習的な語及び単位として用いる語又は縦書の場合には漢数字を用いるものとする。
(符号)
第6条 符号の用い方は、次に掲げる例による。
(1) 「。」(句点)は、1つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。「括弧」の中でも文の言い切りには同じように用い、「・・・すること。」、「・・・するとき。」などで終わる項目にも用いる。
(2) 「、」(読点)は、1つの文の中で語句の切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。
(3) 「.」(ピリオド)は、単位を示す場合、見出し記号に付ける場合及び省略符号とする場合に用いる。
(4) 「・」(なかてん)は、外国語の区切りとか事物の名称を列挙する場合に用いる。
(5) 「~」(なみがた)は、「・・・から・・・まで」を示す場合に用いる。
(6) 「―」(ダツシユ)は、語句の説明や言いかえ及び目次の章名、節名等の次にその章・節等の中に含まれる条名を示す場合などに用い、また、丁目・番地などを省略する場合に用いる。
(7) 「「」」(かぎ括弧)は、ことばを定義する場合、他の用語又は文章を引用する場合などに、その部分を明示するのに用いる。
(8) 「()」(括弧)は、語句若しくは文章の後に注記を加える場合又は見出しその他簡単な独立した語句の左右又は上下を囲む場合に用いる。
(9) 「ヽヽヽ」(点線)は、「ヽヽヽからヽヽヽまで。ヽヽヽすることが」など語句の代用などに用いる。
(例規文の作成諸則)
第7条 本組合における例規文の作成諸則は、次の各号のとおりとする。
(1) 条例、規則及び規程形式をとる告示、訓令等(以下「条例等」という。)は、新たに制定するときは、必ず題名を付けること。この場合において、題名は、要約して簡略にすること。
(2) 条文の数が多い場合は、事項別に適宜、章、節等に分けて整理すること。この場合、題名の次に原則として目次を付けること。
(3) 条文の理解を容易にするため、条文の左上部に「括弧見出し」として、その条文の規定事項の内容を略記すること。この場合、数個の条文が同一種類の事項を規定するときは、これをまとめて最初の条文にだけ付けること。
(4) 同一条文の項が2以上になるときは、第2項以後の項にアラビア数字で番号を付けること。条を置かない場合は、各項にも項番号を付けること。
(5) 引用する法令又は条例等は、その題名だけでなく、その公布年及び番号を必ず記載すること。
(6) 同一の法令若しくは条例等の引用又は同一の名詞の使用が2回以上にわたるときは、最初の条文に以下簡略にする旨を規定し、2回以後は略記する。
(7) 条例等中、既に改正された条項を再び改正する際に、題名の次に公布年、番号を記載する必要があるときは、最初の年、番号を用いる。ただし、全部改正のものについては、全部改正のときの年、番号とする。
(8) 条例等の中で定義を下す場合、その定義の条文に限って用語にかぎ括弧(「 」)を付けること。
(9) 文章の終わりには、必ず句点(。)を付けること。号や( )の中の文章が名詞で終わっているときは、句点を付けない。ただし、「こと」や「とき」で終わるときは付けること。また、名詞形の字句で終わった文章の後に更に文章が続くときも付けること。
(10) 主語の次には、必ず読点(、)を付けること。また、「かつ」の前後、「ただし」の次にも付けること。
第8条 本組合における法規文の形式及び用字の配置は、次に掲げる例による。
(1) 条例又は規則を新たに制定する場合
ア 章節に区分する場合


① 公布文の初字は、第2字目とする。また、公布文が2行以上になるときの第2行目からは、第1字目から書き続ける。
② 公布年月日の初字は、第3字目とする。
③ 公布者の職名と氏名の間は、2字分を空白とし、終わりから第3字目に終わるよう適当に配字する。なお、原本には、管理者の署名を要する。
④ 条例(規則)番号の記号の初字は、第1字目とする。
⑤ 題名の初字は、第4字目とする。なお、題名が2行以上にわたるときは、適当なところで行をかえ、第2行目の字は第4字目とし、肩をそろえて書く。
⑥ 目次の初字は、第1字目とし、2字の間を1字分あけること。
⑦ 目次の章の番号の初字は、第2字目とし、1字分あけて事項を書く。
⑧ 目次の節の番号の初字は、第3字目とし、1字分あけて事項を書く。なお、目次の章、節に入れる条名は、2箇条のときは「・(なかてん)」で結び、3箇条以上のときは「―(ダッシュ)」で結び、括弧する。
⑨ 目次の附則の初字は、第2字目とし、2字の間を1字分あける。
⑩ 本則の章の番号の初字は、第4字目とし「章」の次の1字分あけて事項を書くこと。この場合、事項が「総則」などのように2字のときは、各字の間を1字分あけて書くこと。
⑪ 見出しの括弧は、第2字目とする。
⑫ 条名の初字は、第1字目とし、条文は条名の「条」の字の次を1字分あけて書き始めること。2行以上に及ぶときは、第2字目から書き続けること。
⑬ 本則の節の番号の初字は、第5字目とする。
⑭ 同じ条で項が2項以上になるときは、第2項以下の各項に2、3と番号を付け、項の番号は第1字目に書くこと。項の条文が2行以上にわたるときは、第2行目からは第2字目から書き続けること。
⑮ ただし書は、本文と接続させる。
⑯ 号の番号は、第2字目とし、(1)、(2)の記号を用いる。号の条文が2行以上になるときは、第3字目から書き続ける。
⑰ 号を細分するときは、ア、イ、ウ、エ、オの記号を用い、第3字目から書くこと。
⑱ 附則の初字は、第4字目とし、2字の間を1字分あけて配字すること。
⑲ 附則が項で成り立っているときで、その項数が2以上のときは、第1項から1、2、3…と項番号を付け、初字は第1字目からとし、2行以上にわたるときは、第2字目から書き続けること。なお、附則が1つ項のみのときは、項番号を付けず、初字は第2字目からとすること。また、附則で複雑な内容を規定するような場合、これを項だけに区分すると、項数が非常に多くなって、項に見出しを付けても、わかりにくくなるときは、条に区分する。
イ 本則を条以下で構成する場合
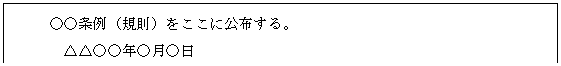
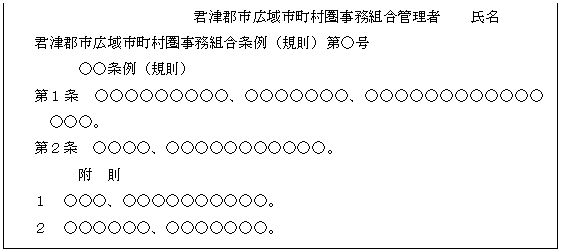
用字の配置は、章節に区分した場合と同様とする。
(2) 条例又は規則の全部を改正する場合
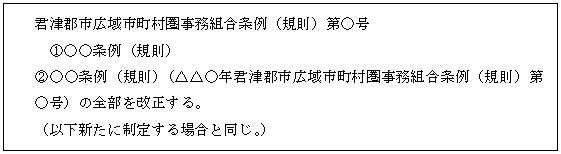
① 題名は、改正した新しい条例(規則)の題名を掲げ、「何々条例(規則)の全部を改正する条例(規則)」などとしないこと。
② 制定文の初字は、第2字目とし、行を移すときは第1字目から書き続けること。
2 法規文の一部を改正する場合の形式及び用字の配置は、次の各号の例による。
(1) 一般的な改正の場合
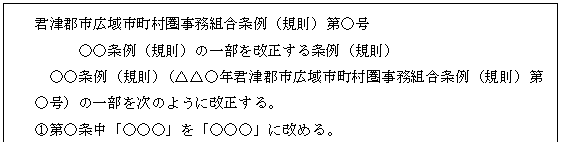
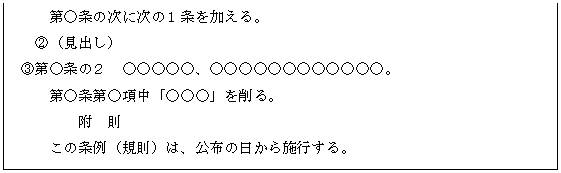
① 初字は第2字目とし、2行以上にわたるときは第1字目から書き続ける。
② 見出しは、条名に付随するものとして取り扱う。
③ 条名の初字は、第1字目とする。
(2) 二つ以上の条例又は規則を一括して改正する場合
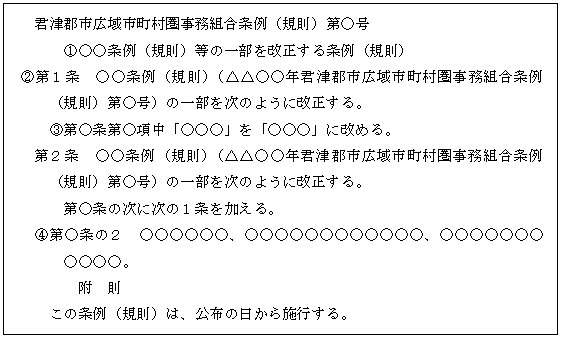
① 最初の一つの条例(規則)の題名を掲げ、その次に「等」の字を加えること。
② 改正する条例(規則)ごとに条を設けること。
③ 柱書きの初字は、第3字目とする。
④ 条名の初字は、第2字目とする。
3 前項に定めるもののほか、法規文の一部を改正する場合の形式は、次の各号の例による。
(1) 既存の条例又は規則の条、項又は号の一部を改正する場合
ア 既存の条項中の一部を改めるとき。
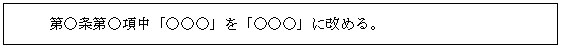
イ 既存の条例又は規則の条項中に文言を追加するとき。
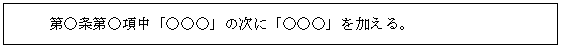
ウ 既存の条例又は規則の条項中の文言を削るとき。
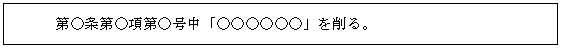
(2) 既存の条例又は規則の条、項又は号の追加をする場合
ア 一般的な場合
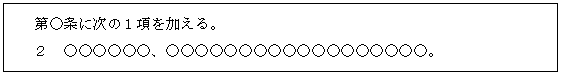
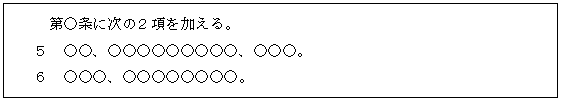
イ 条と条との間に条を加える場合
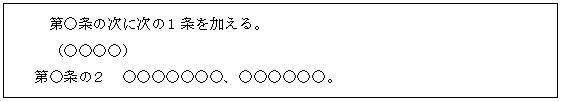
ウ 本則の末条の次に条を加える場合
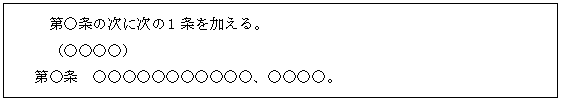
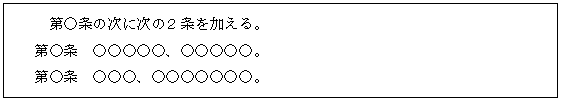
エ 既存の条例又は規則の条、項又は号の中間に、新たに条、項又は号を加える場合
(ア) 次の条、項又は号を一つずつ繰り下げ、あいた箇所に新しい条、項又は号を加える場合
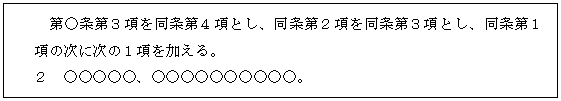
(イ) 既存の条又は号の名称の変更をさける必要がある場合

(ウ) 既存の条例又は規則の条項に、ただし書又は後段を加える場合
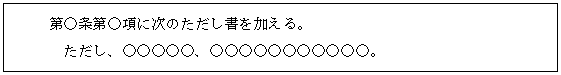
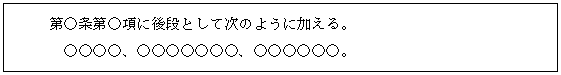
(エ) 条を既存の条例又は規則の章、節等の最後に追加する場合
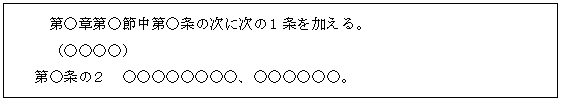
(3) 既存の条例又は規則の一部改正の内容が、既存の条、項又は号の全部の改正である場合
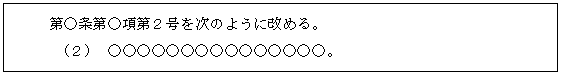
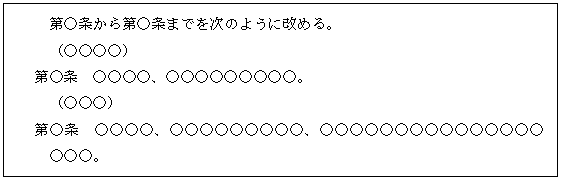
(4) 既存の条例又は規則の一部改正の内容が、既存の条、項又は号の廃止である場合
ア 条例又は規則の最後の条又は条文中の最後の号のように、全く廃止してしまってよい場合
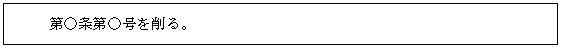
イ 条又は号を削って、後の条又は号を繰り上げてもよい場合
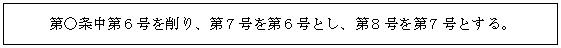
ウ 条又は号を削って、後の条又は号を繰り上げることが不適当である場合
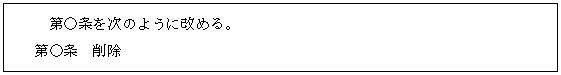
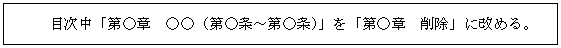
(5) 既存の条例又は規則の章、節等の全体又は章名、節名等を改正し、追加し、又は削除する場合
ア 章名、節名等を改める場合
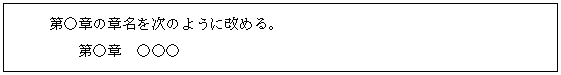
イ 章名、節名等のほか、章、節等に含まれる条文を全部改める場合
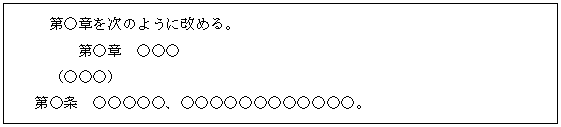
ウ 章、節等のない条例又は規則に新たに章、節等の区分を設ける場合
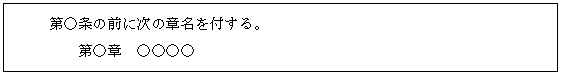
エ 章、節等を、その中に含まれる条文を含めて新たに加える場合
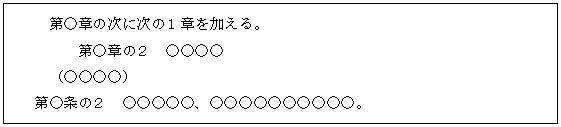
オ 章名、節名等のみを削る場合
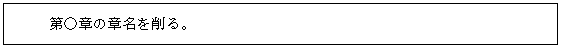
カ 章名、節名等及びこれに含まれる条文全部を削る場合
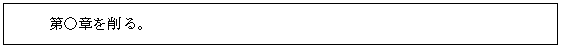
キ 章名、節名等を削ることが不適当である場合
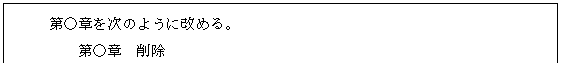

(6) 既存の条例又は規則の一部改正の内容が、既存の条、項又は号の一部を改めるとともに、新しい条、項又は号を加え、あるいは削る場合
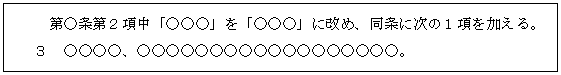
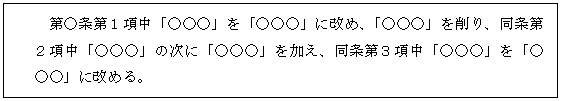
(7) 既存の条例又は規則の一部改正の内容が、既存の条、項又は号を削るとともに、新しい条、項又は号を加える場合
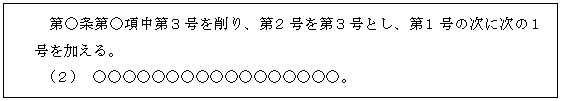
4 法規文を廃止する場合の形式及び用字の配置は、次の各号の例による。
(1) 本則で廃止するときの一般的場合
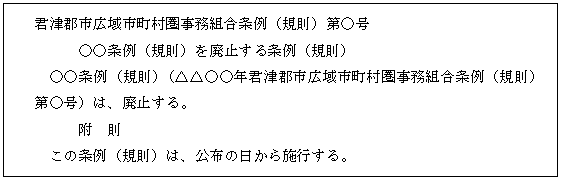
(2) 二つ以上の条例又は規則を一つの条例又は規則で廃止する場合
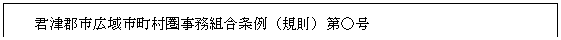
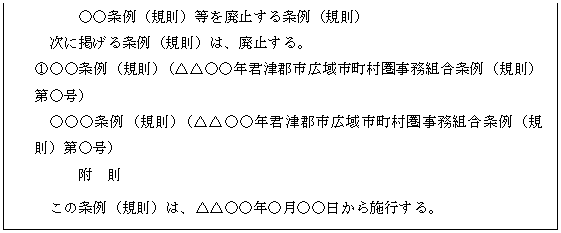
① 列記する条例(規則)の名称の初字は、第2字目とする。
(3) 附則で廃止するときの一般的場合
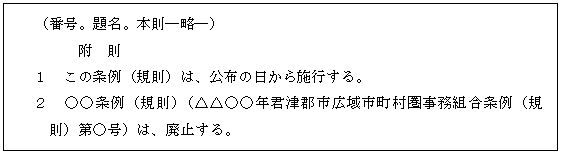
5 法規文の附則の形式は、次の各号の例による。
(1) 施行期日を附則によって確定的に定める場合
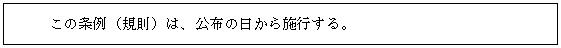
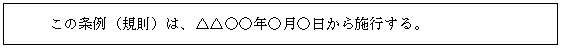
(2) 条例又は規則の施行期日と異なる適用期日を定める場合
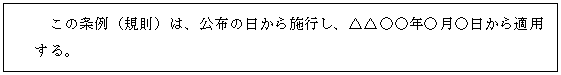
(3) 条例又は規則の施行期日を条例又は規則の附則に規定せず、他の条例又は規則の規定に委任する場合
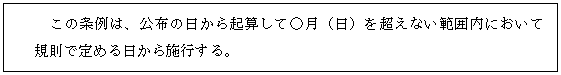
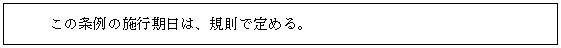
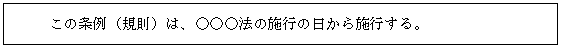
(4) 特別の施行期日を定める場合
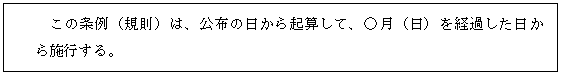
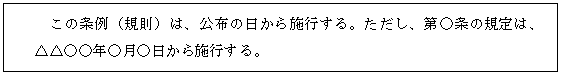
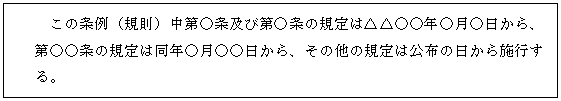
第9条 本組合における公示文の形式及び用字の配置は、次に掲げる例による。
(1) 告示
ア 規程形式のものの場合
(ア) 新設する場合
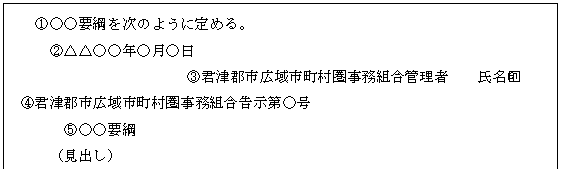
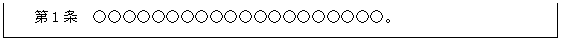
① 制定文の初字は、第2字目とし、2行以上にわたるときは、2行目から第1字目とする。
② 公示年月日の初字は、第3字目とする。
③ 職名と氏名の間は、2字分を空白とし、末尾から3字目で終わるよう適当に配字する。
④ 告示番号の初字は、第1字目とする。
⑤ 題名以下は、法規文の書式の例による。
(イ) 全部改正する場合
新設する場合の例による。この場合、題名の次に「○○要綱(△△○○年君津郡市広域市町村圏事務組合告示第○号)の全部を改正する。」と書く。
(ウ) 一部改正する場合
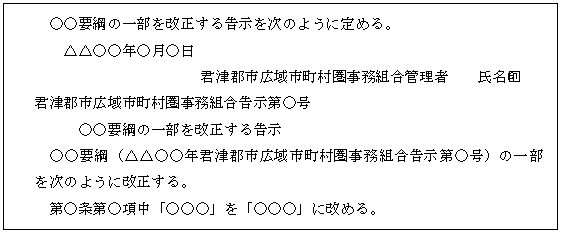
用字の配置は、新設する場合と同様とする。
(エ) 廃止する場合
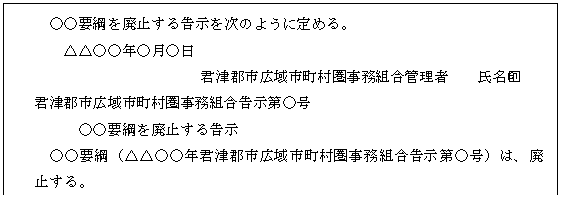
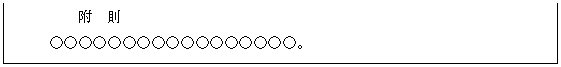
用字の配置は、新設する場合と同様とする。
イ 規程形式をとらない場合
(ア) 新設する場合
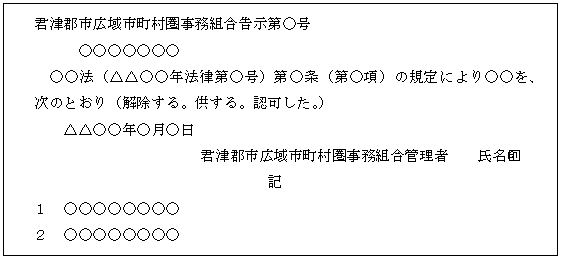
「記」は、左右の中央部に書くこと。
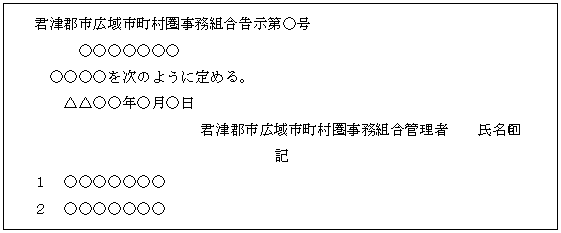
(イ) 改正する場合
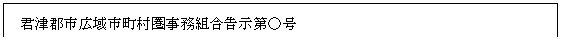
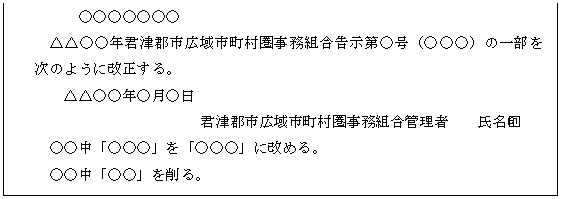
(ウ) 廃止する場合
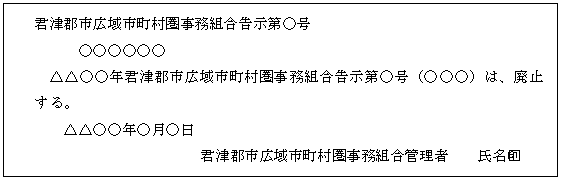
(2) 公告
(ア) 新設する場合
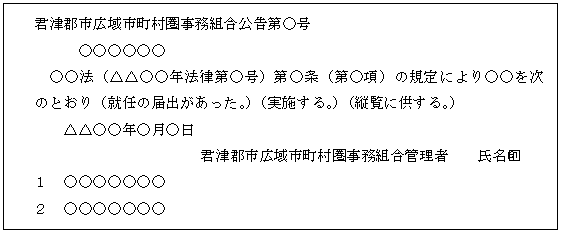
(イ) 変更する場合
公告した事項について変更を生じた場合は、一部改正の方法をとらず、別の公告で変更事項を公示する。
第10条 本組合における令達文の形式及び用字の配置は、次に掲げる例による。
(1) 訓令
ア 規程形式のものの場合
(ア) 新設する場合
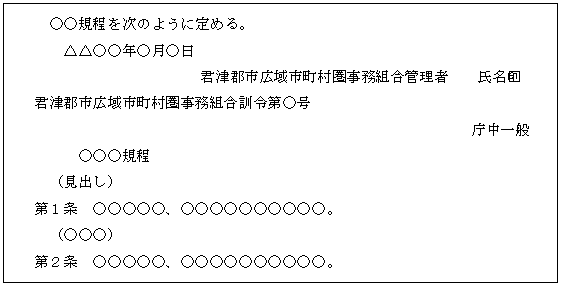
(イ) 一部改正する場合
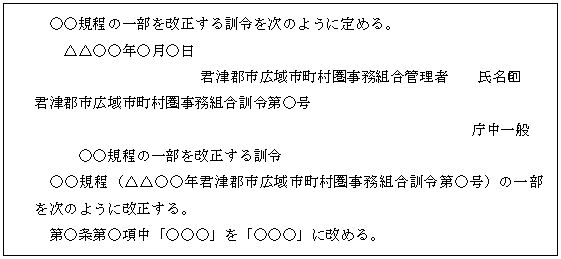
(ウ) 廃止する場合
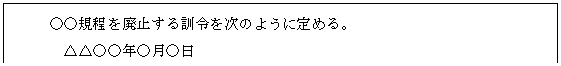
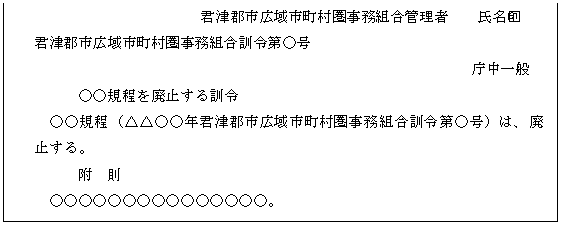
(2) 内訓
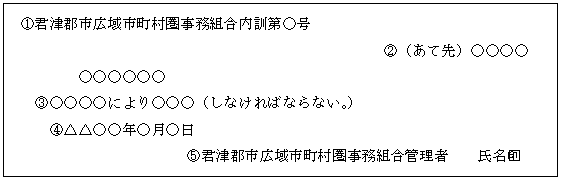
① 内訓番号の初字は、第1字目とする。
② あて先の初字は、末尾から第10字目とする。
③ 本文は、第2字目からとし、2行以上にわたるときは、2行目からは、第1字目とする。
④ 日付の初字は、第3字目からとする。
⑤ 管理者名の文字は、末尾から第3字目に終わるようにする。
(3) 達
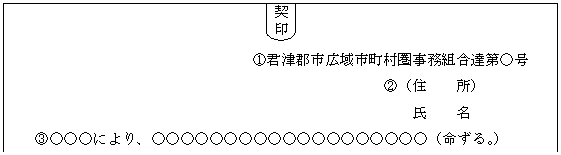
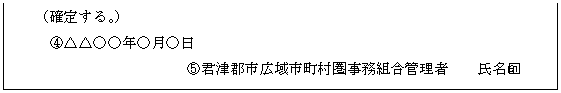
① 達番号は、末尾から第2字目に終わるようにする。
② あて先の初字は、末尾から第10字目とする。
③ 本文の初字は、第2字目からとし、2行以上にわたるときは、2行目からは、第1字目とする。
④ 日付の初字は、第3字目からとする。
⑤ 管理者名の文字は、末尾から3字目に終わるようにする。
(4) 指令
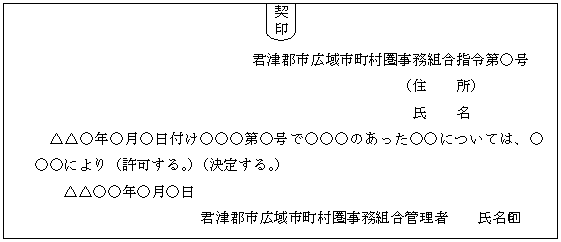
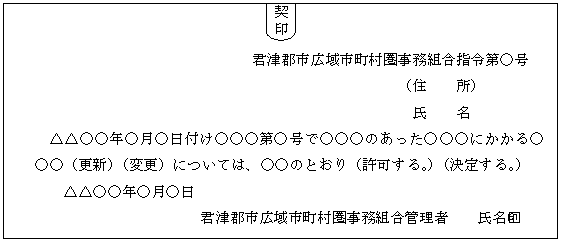
第11条 往復文とは、行政機関が行政機関相互において、又は特定の相手方に対して、ある一定の事項を通知し、照会し、回答する等なんらかの意思を表示する場合に発する文書をいい、その文例は、次のとおりとする。
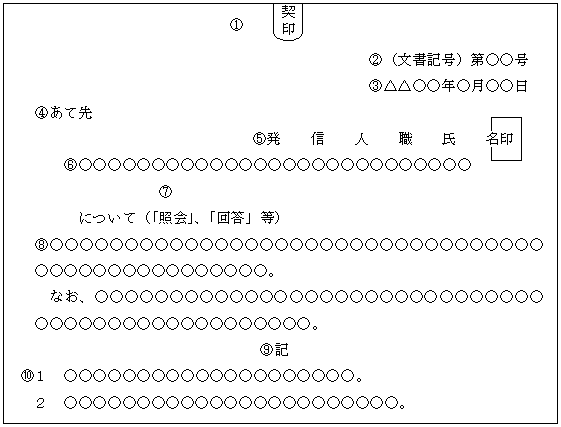
① 契印は、用紙の中央に起案文書に3分発送文書に7分かけて押す。
② 文書記号及び文書番号の初字は、用紙のやや右から書き出し、終字は右から第2字目となるように適当に配字する。
③ 発信年月日は、文書記号、文書番号の下に、初字、終字が上段とそろうよう配字する。
④ あて先は、官公職名だけを原則とし、必要な場合だけ氏名を付記することとし、発信年月日の1行おいて下から書き出し、初字は第2字目とする。
⑤ 発信者は、あて名の1行おいて下に、用紙の中央やや左から書き出し、公印は発信者名の終字にかけて押し、印影の右は1字分あける。
⑥ 件名は、発信者名の2行下に記載し、初字は第4字目とし、終字はその行の終わりから第3字目とする。
件名が長く、行を改めるときも同様とする。
⑦ 括弧の中は、照会、回答、通知等の文書の種類、性質を表す字句を記入する。
⑧ 本文は、件名の下に書き、初字は第2字目とし、2行目からの初字は第1字目とする。
「なお」、「おって」、「ついては」等で文を接続する場合は、行を改めて第2字目から書く。
⑨ 「記」は、本文から行を改めて行の中央に書く。
⑩ 記書きの場合、事項が二つ以上に及ぶときは、それぞれの項の第1字目に見出し記号をつけ、第3字目から書き出す。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成16年8月27日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。